体重減少 WEIGHT-LOSS
体重減少の症状は
ありませんか?

ダイエットによる減量とは異なり、医学的に問題とされる体重減少とは、普段通りの生活をしているにもかかわらず、半年から1年の間に体重が4.5kg以上、または体重の5%以上減少することを指します。
体重減少には「食欲が低下して減る場合」と「食欲はあるのに減ってしまう場合」があり、いずれも何らかの疾患が隠れている可能性があります。特に、意図せず1年以内に4.5kgまたは5%以上の減少がある場合は、原因を明らかにするためにも、できるだけ早めに医療機関を受診しましょう。
思いがけない体重の減少
がある場合
体重減少に伴って、このような症状はありませんか?
- 体重がどのくらい減ったか、またそれがどの期間で起きたか
- 服やベルトが緩くなってきていない
- 気分の落ち込みや、これまで楽しめていたことへの関心の低下はないか
- 腹痛・下痢・発熱・動悸・手の震えなどの症状が出ていないか
- (女性の場合)月経の周期が乱れていないか
など
生活習慣が変化していませんか?
- 食欲は保たれているか
- 最近の生活に大きな変化やストレスがなかったか
- 運動量が増えていないか(スポーツなど含む)
- 服用している薬やサプリメントの影響はないか
- 現在、何か疾患の治療中でないか
など
体重が減少する
メカニズム
体重が減る主な原因は、食事から得られる摂取エネルギーと、日常生活や基礎代謝で消費されるエネルギーのバランスが崩れることによるエネルギー不足です。
また、体重の約3分の2を占める水分が過剰に失われると、脱水状態となり、体重が減少することもあります。
体重減少を伴う
疾患と症状
神経性食欲不振症(拒食症)
ダイエットをきっかけに、体重が増えることへの強い恐怖感から、極端な食事制限や嘔吐、下剤の乱用を行ってしまうケースがあります。これが「神経性食欲不振症(拒食症)」です。
重症化すると、短期間で体重が20%以上減少することもあり、深刻な栄養障害に陥ります。女性では無月経が3ヶ月以上続くことがあり、さらに重篤な場合は不整脈を起こし、生命の危険に及ぶこともあります。
糖尿病
糖尿病は、膵臓から分泌されるインスリンの働きが弱まる、または分泌そのものが不足することにより、血糖値が高くなる疾患です。インスリンの作用が不十分になると、食事で摂取した糖質を効率良くエネルギーに変えることができなくなります。代わりに、体は脂肪や筋肉などのタンパク質を分解してエネルギーを補おうとするため、体重が徐々に減っていきます。
甲状腺亢進症(バセドウ病)
甲状腺亢進症(バセドウ病)は、甲状腺ホルモンの過剰分泌によって代謝が活発になる疾患です。自己免疫の異常や遺伝的要因が関係しており、特に20〜30代の女性に好発します。
食欲が旺盛になる一方でエネルギー消費が著しく高まり、体重が減少するのが特徴です。その他、甲状腺の腫れ、動悸、手の震え、多汗、下痢、疲労感、眼球突出など、様々な症状が起こります。
慢性胃炎、胃・十二指潰瘍
慢性胃炎や胃・十二指腸潰瘍では、胃もたれや胃痛、吐き気、食欲低下などの症状が現れ、食事量が減って体重が落ちることがあります。
特に慢性胃炎を繰り返すと、胃潰瘍へ進行する可能性があるため注意が必要です。
胃潰瘍と十二指腸潰瘍は似た症状が現れますが、痛みの出るタイミングが異なります。食事中~食後にみぞおちが痛むのは胃潰瘍、空腹時や明け方の痛みは十二指腸潰瘍の可能性が高いとされています。
潰瘍性大腸炎
潰瘍性大腸炎は、大腸粘膜に炎症が生じ、びらんや潰瘍ができる慢性の疾患です。20代の若い世代に多く発症し、再発を繰り返すのが特徴です。
主な症状としては、粘液や血液を含む下痢が続き、病状が進行すると腹痛や発熱といった全身症状が現れます。慢性的な下痢によって栄養の吸収が妨げられ、体重が徐々に減少していく傾向があります。
胃がん・大腸がん・膵臓がんなど
胃や大腸、膵臓といった消化器にがんが発生すると、がん細胞が体内の栄養を消費してしまい、体重が減少する原因となります。
さらに、消化管の働きが妨げられることで、腹痛や食欲不振、発熱といった症状が現れることもあります。
体重減少が
見られた場合の検査
体重の減少に明らかな原因がない場合、何らかの疾患が隠れている可能性があります。まず問診で症状や生活習慣を詳しくお伺いしたうえで、必要に応じて以下のような検査を行い、原因の特定を目指します。
胃カメラ検査

口から細いスコープを挿入し、胃粘膜を直接観察する検査です。
大腸カメラ検査

肛門からスコープを挿入し、大腸全体の粘膜を観察する検査です。
腹部超音波検査

腹部に超音波を照射し、肝臓、胆のう、膵臓などの臓器に異常がないかを調べます。
血液検査

採血によって栄養状態や炎症の有無、内臓機能などを幅広く評価します。
生活習慣で
予防できること
ストレスを解消する
生活習慣病は、日常的なストレスにより生活リズムが乱れることで発症することがあります。そのため、日頃からストレスを溜め込まないよう意識することが大切です。
仕事のことは休日には忘れ、しっかり休息を取る時間を確保しましょう。自分に合った趣味や軽い運動などを取り入れることで、効果的なストレス発散に繋がります。
また、良質な睡眠はストレスへの耐性を高める要素でもあります。寝る前に40℃以下のぬるめのお湯で入浴したり、ストレッチをするなどの習慣を取り入れると、質の良い睡眠に繋がります。
過度なダイエットや
極端な偏食を避ける
無理な食事制限や偏った食生活は、心身のバランスを崩す原因になります。炭水化物・タンパク質・脂質・ビタミン・ミネラルなど、五大栄養素をバランス良く取り入れることが基本です。
過度なカロリー制限を続けると、栄養不足により体調不良を引き起こすだけでなく、精神的な不調にも繋がります。
原因が分からない
体重減少は
当院までご相談ください
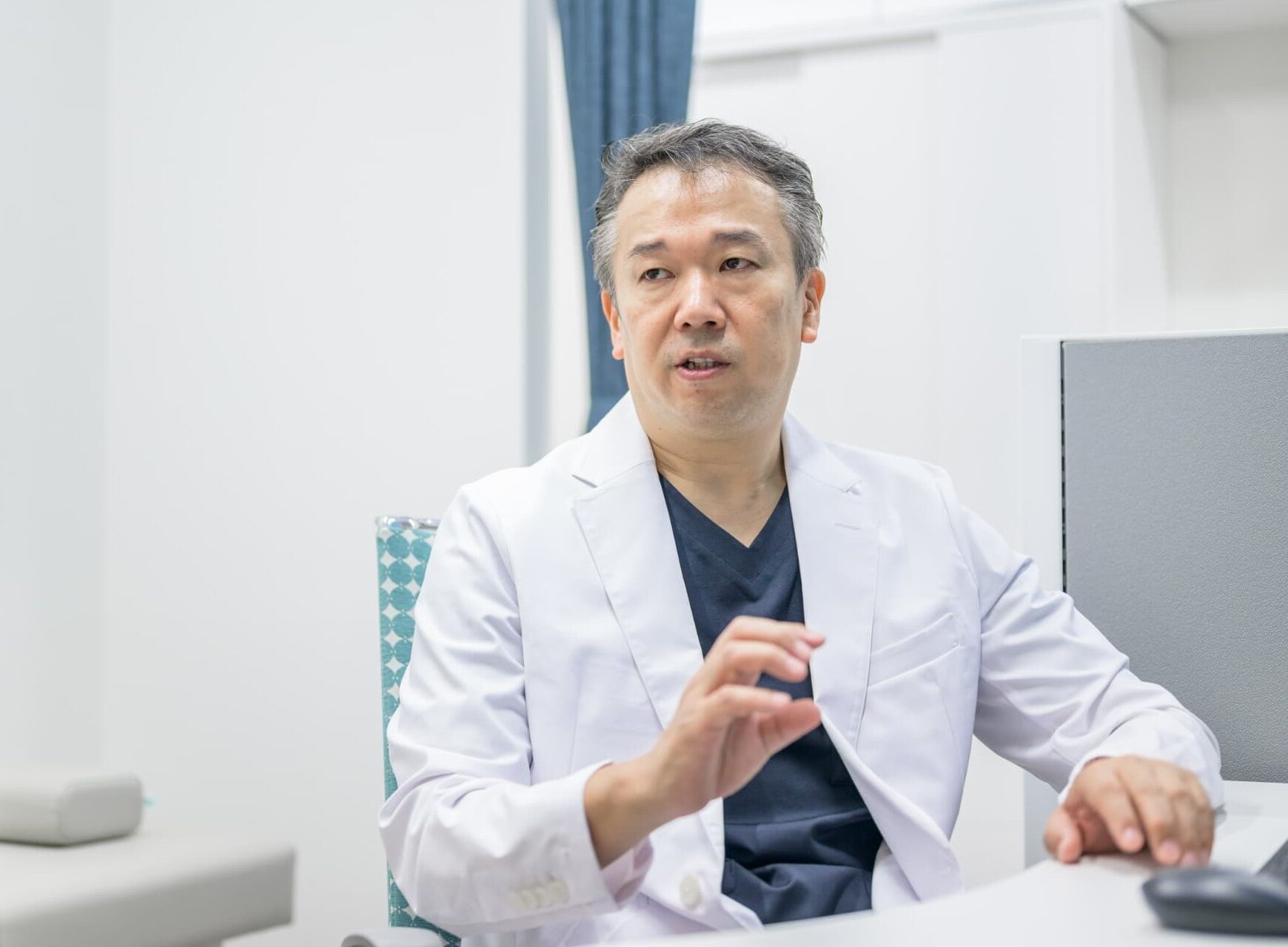
特に食事量に変化がないのに体重が減る、あるいは食欲の低下によって体重が落ちている場合には、内臓疾患や内分泌系の疾患が関係している可能性があります。
気になる症状がある方は、一度当院までご相談ください。




