血便 BLOODY-STOOL
血便が出たら
どうしたらいい?

血便といっても、その状態は様々です。便の一部に血が混じる場合や、便全体が黒く変色する場合、さらには目に見えない微量の出血が含まれていることもあります。このような微量の出血は、便潜血検査によって初めて判明することもあります。
血便は、消化管のいずれかの部位で出血が起きているサインです。なかには大腸がんなど重大な疾患が原因となっていることもあるため、血便に気づいたら早めに消化器内科を受診し、出血の場所を特定して治療を受けることが重要です。
受診時には、便の色や形状、血の混ざり方などを詳しく伝えていただくと、検査がよりスムーズに進みます。
血便と下血は同じ?
違う?
原因の疾患は?
血便と下血は似た言葉ですが、医学的には異なる状態を指します。下血とは、肛門から出る血液全般を意味し、出血源は食道・胃・十二指腸・小腸・大腸など、消化管のあらゆる部位に及びます。血が混ざった便や、血液だけが排出される場合も下血に含まれます。
一方、血便は下血の一部で、主に大腸からの出血によって血の混じった便が出る状態を指します。
下血
食道や胃、十二指腸、小腸、大腸など、消化管のいずれかの部位で出血が起きていることを指します。
血便
下血のうち、特に大腸など下部消化管からの出血によって便に血が混ざる状態を指します。
出血の色で原因疾患の予測
鮮やかな赤い血が混ざっている場合は、肛門やその近くの大腸からの出血が疑われます。
一方で、黒っぽい便や暗赤色の便は、胃や十二指腸といった上部消化管からの出血が疑われます。出血した血液が消化液によって酸化されることで、便が黒く変色するためです。このタイプの血便は「メレナ」とよばれることもあります。
主な血便の疾患(肛門の疾患?大腸の疾患?)
血便は、大腸や肛門に関連する疾患の症状として現れることがあります。原因となる主な疾患には、以下のようなものが挙げられます。
肛門の疾患
いぼ痔
内痔核と外痔核に分けられます。
主に排便時の強いいきみや、妊娠・出産などが原因となって発症します。
切れ痔
慢性的な便秘や下痢が原因で肛門の皮膚が裂け、出血を伴うことがあります。この出血が便に混ざることで、血便として現れます。
肛門ポリープ
繰り返す切れ痔によって形成されるポリープです。このポリープが裂けることで出血し、血便として現れる場合があります。
大腸の疾患
大腸ポリープ・大腸がん・直腸がん
これらの病変に便が触れることで出血を引き起こし、鮮やかな赤い血が多量に見られることがあります。
直腸粘膜脱
排便時の強いいきみにより、直腸粘膜が肛門外に脱出する状態です。この際に出血が起こると、血液が便に混ざり血便として現れることがあります。
大腸憩室出血
大腸壁にできた憩室にある血管が破れて出血する状態です。場合によっては、大量に出血することもあります。
虚血性腸炎
大腸粘膜への血流が不足し、炎症が起きている状態です。出血を伴うことがあり、血便として現れる場合があります。
血便の検査
問診により、血便の色や量、性状などを詳しく伺います。これらは、緊急性の判断や適切な検査方法を選ぶうえで重要な情報となります。
続いて、必要に応じて胃カメラ検査や大腸カメラ検査、レントゲン検査、脈拍・血圧の測定などを実施します。
さらに、血液検査によって炎症の有無や貧血の程度を評価します。
血便の治療
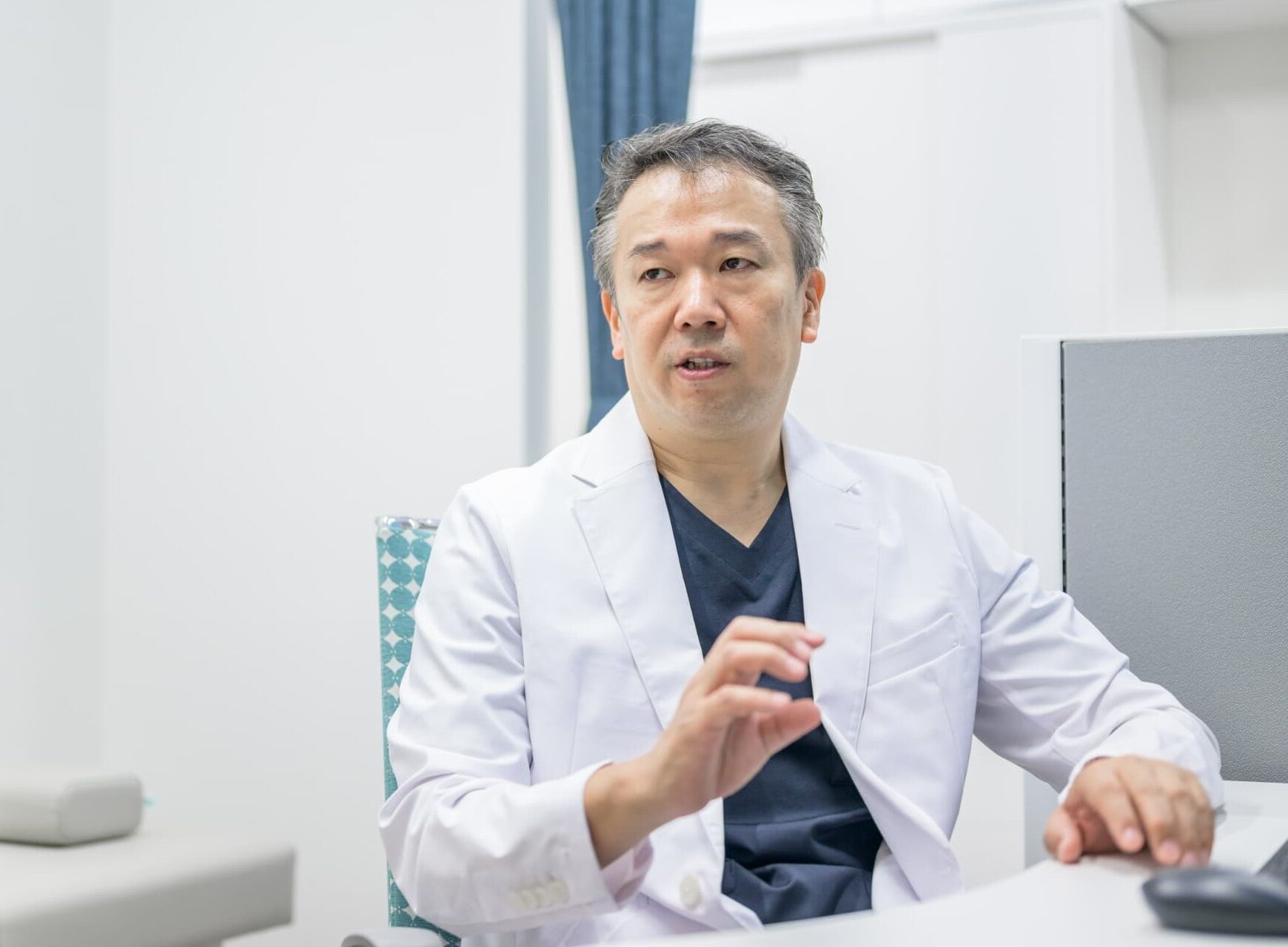
血便が見られても、必ずしも疾患が原因とは限りません。軽度の炎症や一時的な出血であれば、自然に治まるケースもあります。ただし、出血の原因や部位次第では、血便が慢性化したり、深刻な疾患を招いたりする可能性もあります。 そのため、問診や各種検査を通じて原因を特定し、適切な治療を行うことが重要です。
また、血便に伴って下痢や脱水が生じている場合には、それらへの対処も含めて総合的に治療する必要があります。
当院では、大腸カメラ検査により、炎症・ポリープ・がんなどの早期発見と早期治療が可能です。血便に気づいた際は、早めにご相談ください。




